大工手間を計算する
2025.08.31
弊社には社員の大工である小林君が在籍していますが、1人では全ての現場の大工工事は出来ないので外注の大工さんへ工事を依頼しています。
外注の大工さんとは手間賃を決め費用を支払いますが、時には手間が余分にかかり取り決めした金額では足りなくなる場合があります。
こうした時は大工さんと話し合い、足りない費用を弊社からお支払いしています。(お客様からはいただきません)
約30年前、私が下請け大工職人の時に苦労して大工工事が完了した後、人工計算してみたら「あれ手間賃がこんなに安くなってる・・・」という事がありました。
私は元請けの会社に「追加費用をいただけませんか?」と打診しましたが、どの会社も追加の大工手間を出してくれる会社はありませんでした。
この時私は「自社が元請けになったら大工さんへ追加手間が払える会社になる」と決めていました。
あれから約30年
弊社では全ての現場において大工工事終了後、大工さんと取り決めした金額で問題ないか聞いています。
「今回の現場の手間賃で大丈夫ですか?」という問いに対し大工さんは
「大丈夫ですよ、手間が厳しい現場の時は相談しますね」と返答があります。

会社に在籍している小林君担当の現場も大工手間がどの位になっているか?計算します。
外注の大工さんへ依頼する場合の費用をかかった人工で割ると大工手間が算出出来ます。
この数字を見れば、どの位大工手間がかかっているか?が判断出来ます。

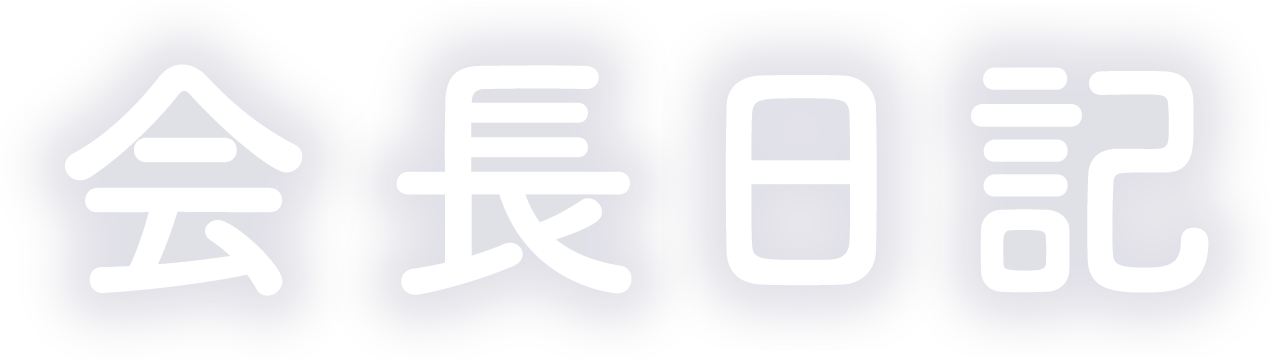



 東の窓と2階北側の天窓、北側のテラスドアから光が入り室内が明るくなるよう設計
東の窓と2階北側の天窓、北側のテラスドアから光が入り室内が明るくなるよう設計





