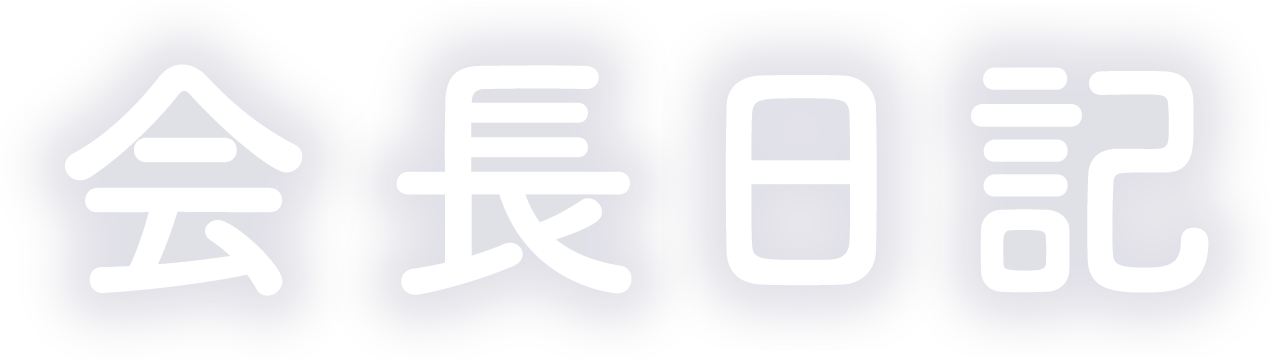基礎工事が完了した後、弊社ではひと手間かけて基礎の養生を行います。
それはコンクリートの急激な乾燥を防ぐ為、外周部の立ち上がりにビニールシートを張ります。

建物内部側の立ち上がりには100ミリの断熱材が貼ってあり水分の放出を抑えられます。
しかし屋外の立ち上がり面はビニールなどで養生しないとコンクリートが急激に乾燥し、クラック(ひび割れ)の原因になります。
こうした問題を克服する為、ビニールシートを張り時間をかけて水分が抜けるよう養生しています。
このひと手間は同業他社ではあまり見ない養生の方法です。
1立法メートルのコンクリートは2300キロの重量があり、この中に水は約180キロ入っています。
この水分を急激に乾燥させるとクラックが入る可能性が高いので、約4か月の時間をかけてゆっくりと水分を蒸発させます。
ちなみにコンクリートの固さを示すスランプという値があります。
一般的に建築物のコンクリートはスランプ18を採用しますが、弊社ではスランプ15を採用します。
スランプ18よりも15の方が水分量が少ないので硬く施工性が悪いのですが、良質な基礎を造る為水分量の少ないコンクリートを採用するのも弊社のこだわりです。
1立法メートル当たりスランプ18は182キロの水に対しスランプ15は176キロなので6キロ少ない計算です。
ここまで基礎工事やコンクリートにこだわる建築業者を私は知りません。
というか、養生の方法やスランプにこだわる会社はほとんど存在しないのが今の建築業界なのです。